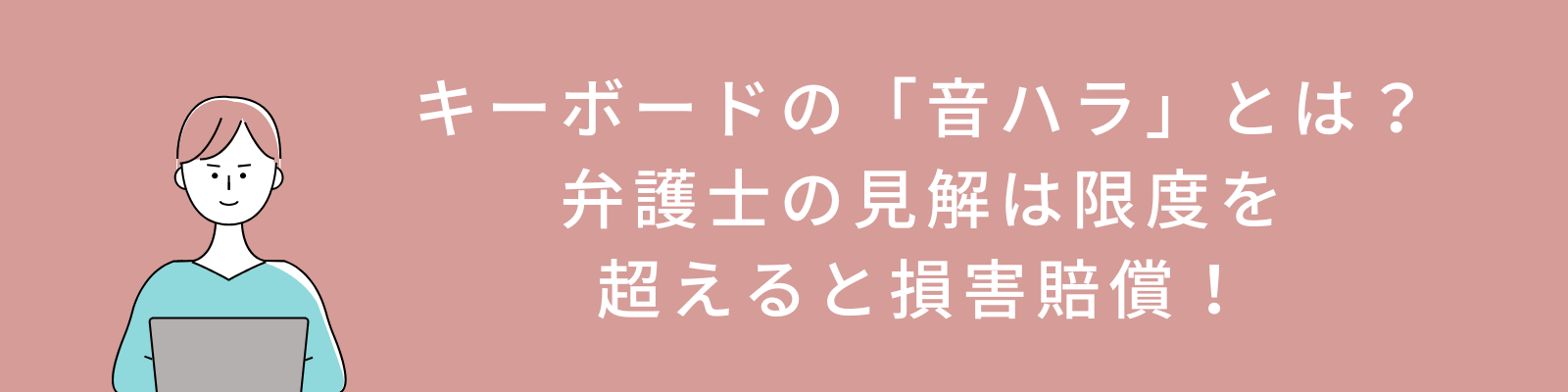
キーボード音ハラスメントとは?
最近、職場や公共の場での「音ハラ(音ハラスメント)」が問題視されることが増えています。特に、オフィスでのキーボードの打鍵音が「うるさい」と感じる人が多く、集中力を削がれたり、ストレスを感じたりすることがあります。本記事では、キーボード音ハラの原因や対策、法的な見解、被害者の声を交えながら詳しく解説します。
<タイピング音クソデカ男がいて、毎日イヤホンしないとストレス>
<机の引き出しをものすごい勢いで閉める音と、マウスを机にガンガンたたきつける音がまじでうるさ過ぎ>
SNS(ネット交流サービス)には、身近な「音」に対する悩みの数々がつづられる。
「ノイズハラスメント」(音ハラ)なる言葉もあるくらいで、職場の騒音トラブルに頭を抱えるビジネスパーソンは少なくない。
出典:毎日新聞
<<<人気商品>>>

キーボード音ハラの原因
1. タイピングの強さ
キーを強く叩くことで、大きな打鍵音が発生します。無意識に力を入れすぎている場合もあり、周囲に迷惑をかけていることに気づかないことが多いです。特に、デスクワークに慣れていない人やストレスを感じている場合、強めのタイピングになりがちです。
2. 爪の長さ
爪が長いと、キーに当たる音が増加し、タイピング音が響きやすくなります。特に、長いネイルをしている人や爪の形状によっては、通常のタイピングよりも音が響きやすくなります。
3. キーボードの種類
メカニカルキーボードなど、一部のキーボードは構造上、打鍵音が大きくなります。特に、青軸のようなクリック音の強いキーボードは、周囲に不快感を与えやすいです。一方で、静音設計のキーボードも存在し、職場や公共の場ではこうした選択肢を考慮することも大切です。
4. 周囲の静けさ
特に静かな環境では、小さな音でも目立ちます。オフィスや図書館、コワーキングスペースなどの静かな場所では、キーボードの音がより気になりやすくなります。周囲の環境によって、音の影響は大きく変わります。
5. オープンスペースの影響
最近では、オープンスペースでの業務が増えているため、個人の音が広がりやすくなっています。壁や仕切りが少ない環境では、キーボードの打鍵音が他の作業スペースにも響くため、注意が必要です。
キーボード音ハラ対策
1. タイピングの見直し
キーを「叩く」のではなく、「押す」感覚でタイピングすることで、音を軽減できます。軽く打つことで、指や手首への負担も減らすことができます。
2. 爪のケア
爪を適切な長さに保つことで、キーに当たる音を減らせます。爪が当たる音が気になる場合は、短めに整えると良いでしょう。
3. 静音キーボードの使用
静音設計のキーボードを使用することで、打鍵音を抑えることができます。メンブレンキーボードや静音赤軸のメカニカルキーボードなどが有効です。
4. キーボードカバーの活用
キーボードカバーを使用することで、打鍵音を吸収し、音を軽減することが可能です。特に、メカニカルキーボードを使用している場合は効果的です。
5. 環境の工夫
ノイズキャンセリングイヤホンを使用することで、周囲の音を遮断し、集中力を高めることができます。また、オフィスでは「音が気になる」と感じる人がいないか確認し、配慮することも重要です。
6. 職場のルール化
オフィスの規則として、特定の時間帯やエリアでは静音キーボードの使用を推奨するなどのルールを設けることで、不要なトラブルを防ぐことができます。
弁護士の見解
キーボードの打鍵音が「音ハラ(音ハラスメント)」として問題視されることがありますが、これが法的にハラスメントと認定されるかは状況によります。一般的に、職場や生活環境で一定の音が発生するのは避けられないため、キーボードの打鍵音が直ちに違法行為と見なされることは少ないと考えられます。
しかし、音の大きさや頻度、時間帯、被害者がその場を離れることが難しい状況など、さまざまな要因を考慮して「受忍限度」を超えると判断される場合、不法行為として損害賠償の対象となる可能性があります。
被害者の見解
音ハラスメント(音ハラ)に悩む被害者の声として、職場での騒音に対する苦情が多く挙げられています。例えば、同僚の強いタイピング音、ドアの開閉音、ペンを机に叩きつける音などが気になり、集中力が削がれるという声があります。また、こうした音がストレスの原因となり、精神的な負担を感じるケースも報告されています。
特に、音に対する感受性が高い人にとっては、職場の騒音が日常的なストレスとなり、業務効率の低下や健康への悪影響が懸念されています。
まとめ
キーボード音ハラスメントは、オフィスや静かな環境で問題となることがあります。自分では気にならない音でも、他人にとってはストレスの原因になることも。適切なタイピング方法や静音キーボードの使用などを取り入れ、快適な作業環境を作ることを心がけましょう。
また、職場ではルールを設けることで不要な摩擦を減らし、従業員がより快適に働ける環境を整えることが重要です。音の問題は、個人の努力だけでなく、組織全体での取り組みが求められる課題であることを意識しましょう。
関連:水原一平の銀行詐欺事件、他に責任を負うべき人物はいるのか?
石丸伸二氏 公職選挙法違反で告発 – 逮捕の可能性はあるのか?
橋本環奈が朝ドラに出ない!降板する不祥事はパワハラが原因なのか?



コメント